『7つの習慣』(スティーブン・R・コヴィー著)は、全世界で四千万部以上を売り上げたベストセラーです。この本には単なる成功法則ではなく、「人格を土台とした人生の原則」が書かれています。それをこの記事では、難しく思える内容をかみくだいて詳しく解説していきます!
序章:7つの習慣読む前に
『7つの習慣』を理解するにあたって知っていてほしい考え方を紹介します。
👓 パラダイム:見方が行動を決める
人の行動や振る舞いは、「パラダイム=ものの見方」によって大きく左右されます。
たとえば、「他人は信用できない」という見方をしている人は、人間関係も行動もぎくしゃくしてしまいます。
しかし、「人は協力できるものだ」と見方を変えれば、人間関係も行動も前向きに変わっていきます。これがパラダイム・シフト(モノの見方を変えるということ)です。
見方を変えることで行動や習慣を変えることができるのです。
🧭 原則:変わらない土台に立つ
どんな見方(パラダイム)を持つかを決めるうえで、指針となるのが「原則」です。正直さ、公正、思いやり、誠実さなどの原則は、流行や気分に左右されず、私たちの考え方や行動をより良いものにするための信頼できる軸になります。
-
P(Production)=成果
-
PC(Production Capability)=成果を生み出す力・土台
例として「金の卵を産むガチョウ」が紹介されています。金の卵(P)ばかり求めて、ガチョウ(PC)を大切にしなければ、やがて何も得られなくなります。
健康、信頼、学び、人間関係など、これらを大事にすることが長期的な成功につながります。
🧩 私的成功と公的成功:まず自立、そして信頼へ
まず第1〜第3の習慣で、自分を律し、責任を引き受ける「私的成功(自立)」を築きます。
次に第4〜第6の習慣で、他者との信頼関係を築く「公的成功(相互依存)」へ進みます。
自立した人だけが、他人とより良い関係を築けるのです。
一時的に好かれるためのテクニックを使ったり、愛想だけを振り撒いたり、という人と深く信頼し合うのは難しいでしょう。
🌱 すべては「自分から始める」こと
『7つの習慣』は、原則に基づいた見方を持ち、自分の内面から変えていく(インサイド・アウト)ことを出発点とします。
そして、PとPCのバランスを保ち、私的成功から公的成功へと成長していく——それが、この本が提案する人生の道です。
🧭 第1の習慣:主体的である
まず初めに、自分の人生について、他人や状況のせいにするということは、自分の人生の舵を他人や状況がにぎっていると認めるということになります。
自分の人生の舵を他人や状況に渡すのではなく、「自分で握る」という姿勢を持つことが大切です。
状況や他人のせいにするのではなく、「自分がどう反応するか」は選べるという気づきが出発点になります。
✅ 例:仕事を失ったとき
大袈裟な例えですが、仕事を失った時、ただ「自分はダメだ」と自己否定して落ち込むこともできます。
でも、「これは新しいことを始めるチャンスだ」と捉えることもできるのです。
🔁 同じ出来事でも「どう受け止めるか(どう反応するか)」は自分で選べる。
「今までの副業に本腰を入れよう」「やりたかった勉強を始めよう」
そんな前向きな行動も、主体的であるからこそ生まれます。
🔄 関心の輪と影響の輪
『第一の習慣』では、「関心の輪」と「影響の輪」という考え方が紹介されています。
- 影響の輪:自分の行動、考え方、学び方、人への接し方など、自分が変えられること
-
関心の輪:天気、政治、景気、他人の評価など、自分では変えられないこと
🟢 主体的な人は、影響の輪に意識を向けて、少しずつ広げていきます。
🔴 反応的な人は、関心の輪ばかり気にして、ストレスや不満を募らせます。
🔧 実践ヒント
-
困難に直面したとき、「ああだめだ」と落ち込むのではなく「今、自分にできることは何か?」と問い直す
-
「やらなきゃ」(何かにやらされている:受動的)→「やると決めた」(自分で決めている:主体的)と言葉を変える(主体的な言葉を使う)
-
他人や環境ではなく、自分が影響できることに集中する
💬 まとめ
困難やトラブルを100%避けることはできません。
でも、どう向き合い、どう行動するかはあなた次第。
そして自分の人生や、毎日にどう向き合い、どう行動するかにこそ主体性が試されます。
それこそが「主体的である」という第一の習慣です。
🧭 第2の習慣:終わりを思い描くことから始める
この習慣は、「自分の人生をどう生きたいのか?」というゴールを明確にした上で、日々の行動や選択を決めていくという考え方です。
「自分の人生をどう生きたいのか?」というゴールや指針がなければ、地図も目的地もなしに彷徨うように旅をするようなものなのです。
逆に「自分の人生をどう生きたいのか?」というゴールや指針があれば、しっかりした地図を持ち目的地に向かって一歩ずつ進んでいけるのです、
🧠 すべてのものは「二度つくられる」
そして『第二の習慣』では、
「すべてのものは二度つくられる」
という原則が語られています。
これは、まず頭の中で思い描く(第一の創造)、その後に実際に行動し形にする(第二の創造)という考え方です。
人生も同じで、ゴールを描かずに動き出すと、望まない場所にたどり着くことがあります。だからこそ、まず「どんな人生を送りたいか」をしっかりと思い描くことが大切なのです。
🎯 例:ゴールがあれば、選択にブレがなくなる
例えば、「家族を大切にしたい」というゴールがある人は、
仕事の誘いや出世話にも流されず、家族との時間を優先するという選択ができます。
これは、目先の損得ではなく、自分の価値観に基づいて行動するということ。
🔎 終わりを思い描く=自分の「最期」から逆算する
『7つの習慣』では、重要なワークとして「自分の葬儀を想像する」というものがあります。
-
その場に誰が来ているか?
-
彼らがあなたのことをどんなふうに語るか?
つまり、終わりを思い描くということは「自分はどう生きたいのか?」を明確にするための問いになるのです。
📜 ミッション・ステートメントを作ろう
ミッション・ステートメントとは、「自分の人生の指針」を言葉にしたもので、いわば自分自身の憲法のような存在です。
企業に理念があるように、私たち個人にも「どんな価値観に基づいて、どう生きるのか」を明文化することができます。これを持つことで、迷ったときに判断基準ができ、ブレずに行動しやすくなります。
これを作る時上の「終わりを思い描く」をぜひ参考にしてください
✍️ 具体例:
-
「私は、家族との絆を何より大切にし、誠実で思いやりのある行動を通じて、信頼される人間でありたい」
-
「私は、学び続ける姿勢を持ち、自分と他人の可能性を信じ、日々成長していく」
-
「私は、自分の強みを活かして社会に貢献し、感謝と謙虚さを忘れずに生きる」
ミッション・ステートメントは1文でも構いませんし、必要なら箇条書きでも構いません。
大切なのは、「こうありたい」と本気で思える自分の軸を見つけることです。
そしてこれがあると、迷ったとき、判断の軸になります。
🔧 実践ヒント
-
💭 自分の葬儀で、周りにどう語られたいかを具体的に想像してみる。
-
🧑🤝🧑 家族、仕事、友人、趣味などの自分の役割ごとに「理想の自分像」を書いてみる。
-
✍️ ミッション・ステートメントを1文でもいいので書いてみる(何度でも書き直してOK)
💬 まとめ
「終わりを思い描くことから始める」は、日々の行動に深い意味を与える習慣です。
ゴールを明確にすれば、忙しい日々の中でも「自分にとって大切なこと」を見失わずにすみます。
ぜひ、今日から1文でもミッション・ステートメントを作るところから始めてみてください。
🕒 第3の習慣:最優先事項を優先する
この習慣では、本当に大切なことを忙しない日々の中で本当に優先できているか?を見直します。この習慣は忘れられがちな「重要だが緊急ではないこと」(例:健康づくり、学習、人間関係)に時間を使う力を育てます。
🕒 「緊急×重要」の4つの領域を知ろう
『7つの習慣』では、すべての行動を次の4つの領域に分類しています:
| 領域 | 内容 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 第Ⅰ領域 | 緊急かつ重要 | 締切のある仕事、病気の対応 | 危機・対処に追われる毎日になりがち |
| 第Ⅱ領域 | 緊急ではないが重要 | 健康管理、人間関係づくり、学び | 将来の質を高める時間 |
| 第Ⅲ領域 | 緊急だが重要でない | 急な電話、無意味な会議 | 他人の都合に振り回されがち |
| 第Ⅳ領域 | 緊急でも重要でもない | ネットサーフィン、だらだらTV | 時間の浪費ゾーン |
私たちが目指すべきは「第Ⅱ領域にもっと時間を使うこと」。
ここの第二領域にこそ、人生の質を高めるために、本当に時間をかけるべき大切なことが集まっている場所なのです。
💡 第二領域を見つける質問
「今はやっていないけれど、習慣にすれば私生活や仕事が良くなることは何か?」
こうした活動こそが“第二領域”であり、日々の中でそれを実行することで、人生の質は大きく変わっていきます。
⚖️ PとPCのバランスと第二領域
この第3の習慣は、「P(成果)とPC(成果を生む能力)」のバランスを取ることにもつながります。
-
P(Production)=目の前の成果・結果
-
PC(Production Capability)=その成果を生み出す力・能力・関係性・仕組み
🛠 例えば:
-
仕事を早く仕上げる(P)ために睡眠を削ると、健康(PC)が失われ、結果として長期的には成果も出せなくなる。
-
子どもに勉強をやらせる(P)ことばかりに注力し、信頼関係(PC)を築かないと、続かなくなる。
このような健康や信頼関係といった、第二領域の緊急ではないが重要な物事は、面倒くさかったり、仕事に追われて忘れられがちです。ですが緊急でないが重要なことは人生で最も重要なことが多いです。
効果的な人は、目先の結果に追われすぎず、「成果を生み続けられる状態」=PCにも投資しています。
つまり、「重要だが緊急ではない第Ⅱ領域」に時間を使うことは、PとPCのバランスを保つための実践でもあるのです。
🔧 実践ヒント:
-
1週間のスケジュールを立て、最も重要な予定(第二領域)を最初に入れる
-
「目の前のこと」より「本当に大切なこと」に焦点を当てたプランを考える
-
SNSやスマホに使う時間を意識的に減らす
🤝 公的成功と「相互依存のパラダイム」とは?
ここではこれから公的成功につながる、第四の習慣から第六の習慣を理解する上で知っておかなければならないことを書いていきます。
『7つの習慣』では、人間の成長を3つの段階で捉えています:
-
依存(Dependence)
他人に頼らなければ何もできない状態
例:「親がやってくれなきゃ無理」「上司が決めてくれないと動けない」 -
自立(Independence)=私的成功
自分の価値観で決断し、責任をもって行動できる状態 -
相互依存(Interdependence)=公的成功
自立した人同士が協力し、1人では成し得ない成果を生み出せる状態
💡 「相互依存のパラダイム」とは?
これは、「他者と協力することで、より大きな成功が得られる」という考え方です。
人生の多くの成功、たとえば職場のプロジェクト、家族との関係、友人との共同作業などは、自分1人の力では完結しません。
そこには信頼関係と協力が不可欠です。
🪴 私的成功が公的成功の土台になる理由
相互依存は「依存」とは違います。
自立していない人同士が組んでも、お互いに振り回され、健全な関係にはなりません。
だからこそ『7つの習慣』では、まず第1〜第3の習慣(私的成功)で「自分の軸」を築くことを重視しています。
自分の価値観や行動原則に責任を持てる状態になってはじめて、他者と建設的な関係を築けるのです。
💰 信用残高:信頼関係の“貯金”
公的成功のカギは「信用残高」にあります。
これは、人との関係における“信頼の貯金”のようなものです。
-
約束を守る
-
相手を尊重する
-
誠実に接する
-
話をよく聴く
こうした小さな行動が積み重なることで、信頼が蓄積されていきます。
そして、信用残高が高い関係ほど、率直な話し合いや協力、Win-Winの関係が築きやすくなります。
逆に、信用残高が低いと、どんなに正論を述べても相手には届かず、関係がギクシャクしてしまいます。
つまり、相互依存のパラダイムを持って公的成功を築くためには、私的成功と信用がなければなしえないというのが『7つの習慣』の考え方なのです。
それを理解した上でここからは第4から6の習慣です!
🕒 第4の習慣:Win-Winを考える
相手も自分も大切にする、成熟した人間関係の基本
「Win-Win」とは、自分も相手も満足できる相互利益を目指す考え方です。
競争や妥協ではなく、「全員が勝者になれる選択肢はないか?」を探る姿勢が、この習慣の核心です。
👤 この本でのWin-Winについて
この本でのWin-Winは単なる交渉術ではなく、
信頼関係を築くための基本的な姿勢です。
「自分の意見を主張する」だけでなく、
「相手のニーズや立場も尊重する」
この両方を大切にすることで、お互いにとって満足のいく関係が築かれていきます。
🧱 3つの土台:「人格・関係・協定」
Win-Winを成立させるためには、以下の3つが土台となります:
-
人格(Character)
→ 誠実さ、成熟(自分も相手も尊重する力)、豊かさマインド(全員にチャンスがあるという前提) -
関係(Relationships)
→ 信頼残高の高い人間関係 -
協定(Agreements)
→ 明確な目的・役割・ルール・評価指標を事前に共有しておく
これらがそろって初めて、Win-Winの関係性は実現します。
❌「Win-Lose」や「Lose-Win」に注意
-
Win-Lose(勝ち負け):自分が勝つために相手を負かす
-
Lose-Win(自己犠牲):自分を犠牲にして相手に譲る
どちらも長期的には信頼を損ね、関係性が壊れていきます。
🛑 No Deal(取引しない)という選択肢
ときには「Win-Winの解決策が見つからない」こともあります。
そんなときには「No Deal(今回は取引しない)」という選択も健全です。
「無理に妥協してLose-Win、または無理に押し通してwin-loseになるくらいなら、関係性を壊してまで、お互いのためにならない取引をしない方が良い」
という冷静な判断が、むしろ信頼を深めることもあります。
🔧 実践ヒント
-
対話の中で「どうすれば両方の満足が得られるか?」を常に意識する
-
「自分が得る=相手が損する」というゼロサム思考から抜け出す
-
お互いのゴールやニーズを共有し、“成功”の定義を再構築する
-
解決できないときは「No Deal」も選択肢に入れる
🕒 第5の習慣:まず理解に徹し、そして理解される
「人はまず、自分が理解されたい」と思っていますが、本当に信頼され、理解される人は「まず相手を理解する」ことから始めます。
この習慣では、相手を理解する力(エンパシー・リスニング)の重要性が強調されます。相手の話を聴く姿勢こそが、良い人間関係や信頼関係を築く鍵となります。
💬 エンパシー・リスニング(共感による傾聴)
エンパシー・リスニングとは、「相手の立場や感情を理解しようとする聴き方」です。
ただ相手の言葉を聞くだけではなく、その人の感情や背景を理解しようとすることが大切です。
たとえば、友人が悩みを打ち明けてきたとき、私たちはつい「どうしたらいいか?」というアドバイスをしたくなりますが、まず大切なのは相手が何を感じているのか、何を思っているのかを理解することです。
📌 例:
-
友人が「最近、仕事がうまくいかない」と話し始めたとき、最初にするべきはアドバイスをすることではなく、共感し、理解することです。
-
「それは辛いね、どんなときに一番つらいと感じるの?」と、相手の気持ちに寄り添いながら話を聴くことで、相手は自分の気持ちを理解してくれると感じ、信頼感が高まります。
🩺 診断してから処方する
傾聴の大切なポイントは、「処方する前に診断する」ことです。
私たちはしばしば、問題を早く解決したくて、すぐにアドバイスや意見を述べがちですが、それでは相手が本当に必要としている解決策にたどり着かないことが多いです。
友人が悩みを話し始めたとき、まずは共感し、その感情を理解し、聞き終わった後に自分の考えを冷静に伝えることが大切です。もしすぐにアドバイスをしてしまうと、相手の感情を無視した形になりかねません。
-
まずは、相手の状況を深く理解する
-
相手がどう感じているのか、何を求めているのかを聴くことが、信頼を築く基本です。
🔧 実践ヒント:
-
話の途中で口を挟まず、最後まで聞く
自分の意見を言いたくなったとしても、まず相手の言葉を最後まで聴きましょう。 -
「どうしてそう感じたの?」と共感を示しながら尋ねる
質問をすることで、相手の思いや背景に理解を深めることができます。 -
相手の背景や立場を意識して聞く
相手の立場や価値観を意識して聴くことで、さらに深い理解が得られます。
🧠 まとめ
「理解される」ためには、まずは「理解する」ことが大切です。
この習慣を実践することで、信頼関係が深まり、より効果的なコミュニケーションが生まれます。相手の心に寄り添い、共感を示すことが、最終的に自分自身の信頼を得る大きな鍵となるのです。
🕒 第6の習慣:シナジーを創り出す
💡 シナジーとは?
シナジー(Synergy)とは、「異なる力や意見を結びつけることによって、個々の力を合わせた以上の結果を生み出す」という考え方です。つまり、個人やチームが協力し合うことで、単独では得られない成果を達成できるというものです。
シナジーを生み出すためには、対立や衝突を恐れず、異なる意見や視点を融合させることが重要です。自分の意見だけを押し通すのではなく、相手の意見を尊重し、共に成長する姿勢が求められます。
🎯 Win-Winの考え方と相手の尊重
シナジーを創り出すためには、Win-Win(双方にとっての成功)の考え方が不可欠です。これを実践するには、相手を尊重し、互いにとって利益のある解決策を模索することが大切です。自分の利益だけを考えるのではなく、相手の立場や意見を尊重し、共に成長する方向を見出すことが、シナジーを生み出す鍵となります。
📌 例:
チームでの企画会議で意見が対立したとき、「どちらかを選ぶ」のではなく、両方のアイデアを組み合わせて新しい提案を考える。これにより、対立を解消するだけでなく、全員が納得できる解決策が見つかる可能性が高まります。この過程で、Win-Winの精神を持ち、相手の意見を尊重しながら新しい価値を創造することが重要です。
🔧 実践ヒント:
-
異なる意見を「面白い」と感じる癖をつける
自分と違う考え方に出会ったとき、それを否定するのではなく「面白い」と感じることで、新たな発想が生まれやすくなります。 -
チームやグループで積極的に参加する
他のメンバーの意見を積極的に聞き、アイデアを出し合うことでシナジーを生み出しやすくなります。 -
「対立」ではなく「融合」を目指す会話をする
自分の意見を通すのではなく、相手の意見と自分の意見を組み合わせて新しい解決策を模索する姿勢を大切にすることが重要です。
🎯 まとめ
シナジーを創り出すことは、異なる意見や個性を活かして新しい価値を生み出すことです。対立ではなく、協力や融合を目指すことで、個々の力を合わせた以上の成果を生み出すことができます。また、シナジーを生み出すためには、Win-Winの考え方や相手の尊重が不可欠です。これらを実践することで、チームや組織全体の成長を促進し、革新的な解決策を見つけることができるのです。
🕒 第7の習慣:刃を研ぐ(自分をメンテナンスする習慣)
「刃を研ぐ」とは、自分自身を定期的にメンテナンスし、成長と充実を保つことです。日々の生活や仕事の中で、心や体、知恵を磨くことを意識的に行うことで、他の習慣を持続可能にし、成長を加速させます。
💡 上向きの螺旋
「刃を研ぐ」の習慣は、自己改善のための上向きの螺旋を生み出します。日々自分を整え、心身を健康に保つことで、他の習慣にも良い影響を与えます。例えば、体調が整っていると仕事に集中でき、知識を深めることにも意欲的になり、結果として成果が上がります。このポジティブな循環が上向きの螺旋です。
🏋️♂️ 肉体的側面:体を整える
健康な体は、全ての活動の土台となります。身体を定期的に動かすことは、エネルギーを高め、心身のバランスを保つために不可欠です。
📌 例: 週3回のウォーキングを続けることで、心身がリフレッシュされ、気分も前向きになり、仕事への集中力も向上します。
🔧 実践ヒント:
-
週3回は軽い運動をする(散歩やストレッチでもOK)
-
毎日のストレッチで柔軟性を高める
日々の軽い運動を習慣にすることで、体調が安定し、日常生活や仕事のパフォーマンスが向上します。
🧠 精神的側面:心を整える
精神的な健康を保つためには、内面的な充実が大切です。ストレスを軽減し、心を落ち着けるためには、意識的にリラックスする時間を設けることが効果的です。
📌 例: 自然の中を歩いたり、深呼吸をして心をリセットすることで、心の静けさが取り戻せます。
🔧 実践ヒント:
-
自然にふれる(公園や山へ行く)
-
毎日の短い瞑想や深呼吸で心を落ち着ける
-
日記をつけることで思考を整理し、感情を把握する
これらの活動を通じて、精神的にリラックスし、心の余裕を持つことができます。心を整えることで、感情のコントロールや人間関係が円滑になり、仕事の効率も上がります。
📚 知的側面:学びを深める
知識を高め、視野を広げることも重要です。継続的に学ぶことで、問題解決能力や創造力が向上します。
📌 例: 毎週1冊本を読むことで、知識や視点が広がり、仕事や人間関係にも新たな洞察を得ることができます。
🔧 実践ヒント:
-
毎週、1冊は本を読む時間を取る
定期的に新しい知識を取り入れることで、自分の成長を促すと同時に、他の人との会話でも新しい視点を提供できます。 -
ポッドキャストやオンライン講座などで新しい知識を吸収する
まとめ
「刃を研ぐ」習慣は、肉体的、精神的、知的な鍛錬を通じて、他の習慣を持続可能にする力を得るっことができます。自分を整えることによって、心身の健康が保たれ、成長のサイクルが生まれます。日々の小さな努力が上向きの螺旋を作り出し、全体的な生活の質を向上させてくれるのです。
終わりに
『7つの習慣』は、読むだけで人生が変わるわけではありません。小さな行動から、日々意識して実践していくことが鍵です。まずは自分がどんな生き方をしたいかを考えてみてください。
そしてぜひこの本を手に取って読んでみてください!
この本を読み実践することでで今日から少しずつ変わっていけるはずです。
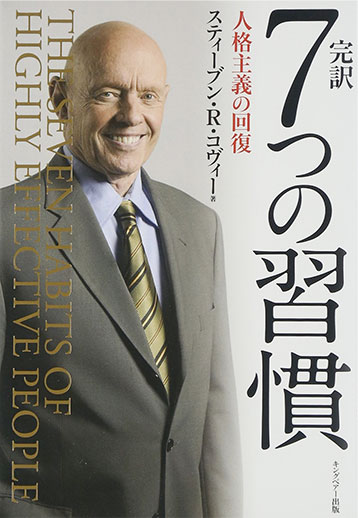


コメント