はじめに
私たちの生活を便利にしてくれたスマートフォン。しかし、やりたいことがあったのにスマホを見ていたら1日が終わってしまった、スマホから離れたいけど離れられない、という悩みは私を含めて多くの方が抱えているのではないでしょうか。
スウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセンによる著書『スマホ脳』では、現代の人々が抱えるスマホ中毒、集中力の低下、不安感、睡眠障害などの問題がなぜ起こるのかを科学的に解説し、解決策を提案してくれています。
この記事では、『スマホ脳』の主な内容(スマホが私たちに与える影響)を解説しながら、私たちがこの問題に立ち向かい、スマートフォンと健全に付き合う方法を解説していきます。
スマホが心身に与える影響

① 集中力の分断
スマートフォンの通知やアプリを開くことは、脳に絶え間ない刺激を与えます。脳はそのたびに「次に注意を向けるべきものは何か」を判断するため、集中力は次第に分散されます。
脳はマルチタスクをしているように見えて、実は一度に一つのことしか処理できません。そのため、通知のたびに集中が中断され、元の作業に再び集中するまでに、平均15〜20分かかると言われています。
さらに、スマートフォンは部屋にあるだけ(通知が鳴らない状態でも)で集中力が落ちるという研究結果が出ています。ですので、何かに集中したいときはできるかぎりスマホを部屋の外に置いてくるまたは、カバンの中にしまうのがおすすめです。
②ドーパミン中毒 — スマホ中毒になる理由
スマートフォンを使うたびに感じる「もっと見たい」「もっと知りたい」という欲求は、実は脳の「快楽物質」ドーパミンによって引き起こされているのです。ドーパミンは、モチベーションや学習、喜び、快楽を司る神経伝達物質で、報酬(食事など)を得たときに分泌されます。
スマホのアプリ、特にSNSや動画のプラットフォームは、私たちの脳を中毒的に刺激するように設計されています。例えば、SNSのタイムラインには新しい投稿が次々と現れ、予測できない情報や画像が表示されます。この「予測不可能性」こそがドーパミンの分泌を促す鍵です。
-
なぜ予測不可能性が重要か?
人間の脳は「報酬」を期待することでドーパミンを分泌しますが、その報酬が予測できない場合、脳は強く刺激されるのです。つまり、「何が出てくるか分からない」状況にこそ、脳はワクワクし、強く反応するのです。これは、狩猟採集時代の人類にとって、どこに食料があるか予測できない環境で未知の場所に食料を探し求めて飛び込むために役立った仕組みだと考えられています。SNSのシステムは、この脳の仕組みを利用し、次に何が起こるか分からない状況を作り出し、常に新しい情報が提供されるため、私たちの脳は次々と反応します。 →ゲームのガチャなども同じシステムですね。
たとえば、Facebookの「いいね!」やInstagramのコメント、YouTubeの自動再生機能など、これらはすべて手間をかけずに得れる「報酬」を脳に提供しており、ドーパミンの分泌を引き起こします。脳はその瞬間の快感を覚え、次回も同じような反応を示すことを期待してしまうのです。
-
ドーパミンと「強化学習」
依存がより強くなってしまうことには、「強化学習」と呼ばれる学習の仕組みとも深く関係しています。強化学習とは、ある行動をとった結果として得られる報酬によって、その行動を繰り返したくなるようにする脳のメカニズムのことです。
SNSの通知や新しい動画を開いたときに得られる「いいね」や刺激的なコンテンツは、脳にとってポジティブな報酬となります。そしてそのたびにドーパミンが分泌され、「またスマホを見たい」という欲求が強くなっていきます。
このように、スマートフォンは多くのドーパミンを出し、それを脳が喜び、それを繰り返しどんどん依存していくのです。
また、脳がドーパミンに依存している状態は、他の報酬(食事や運動、睡眠など)への関心を減らし、スマホの使用に対する欲求を強化していきます。これがいわゆる「スマホ中毒」の原因です。
-
なぜスマホやアプリを中毒になるように作ったのか
この問いに対する答えは明快です。スマホやアプリを使ってくれれば使ってくれるほど、その会社は広告などにより大きな収益を得ます。そのため、皆さんを中毒にすればするほど、アプリ、スマホを開発する会社は莫大な利益を上げられるのです。
③ 睡眠の質の低下
興味深い研究として、アメリカ・ペンシルベニア大学の実験では、「SNSの使用時間を制限することで、孤独感や抑うつ感が軽減された」という結果が報告されました。研究チームは被験者のSNSの使用を1日30分以内に制限したところ、わずか3週間で、精神的な健康状態に明らかな改善が見られたのです。
では、なぜSNSが孤独を招くのでしょうか?
理由の一つは、「比較」による自己否定です。SNSには他人の楽しそうな日常、成功、華やかな瞬間が並びます。それを見る私たちは、「自分は何もしていない」「自分の人生は退屈だ」と感じてしまいやすく、知らず知らずのうちに劣等感や孤独感が募っていくのです。
また、SNSの“つながり”はあくまでデジタル上のものであり、現実の対面でのコミュニケーションや深い共感とは異なります。フォロワー数が多くても、実際には「誰にも本音を話せていない」と感じている人も少なくありません。
つまり、SNSの過剰使用は“つながっているはずなのに、なぜか孤独”という矛盾した状態を引き起こすのです。
どう対処すればよいのか?実践のヒント
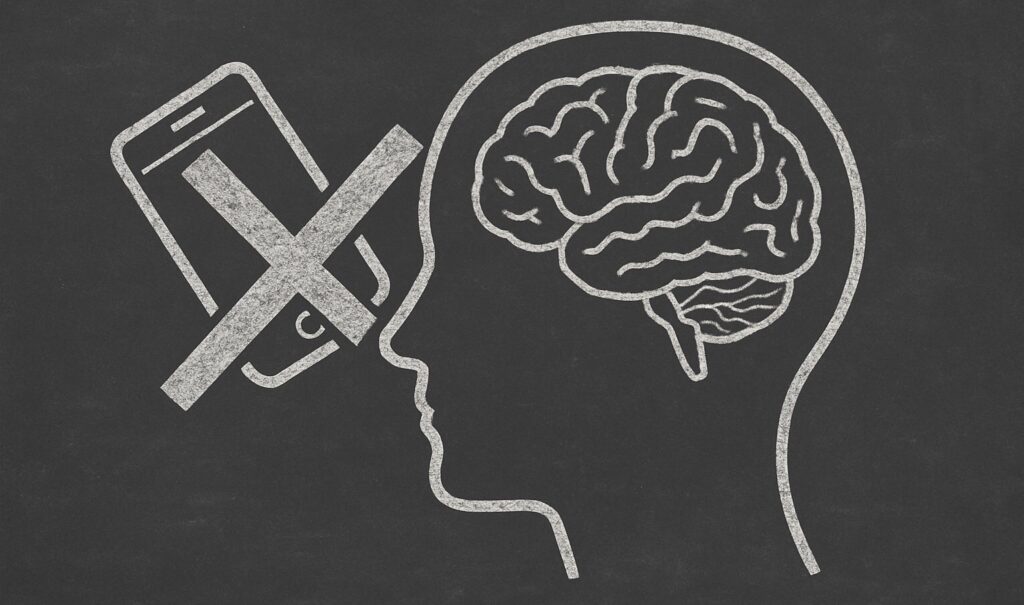
① スマホ断食(デジタルデトックス)を取り入れる
週に1度でも「スマホを見ない時間」を意識的に設けることで、脳がリセットされやすくなります。例えば、毎週日曜の午前中はスマホを完全に手放す、1日のこの時間はスマホを見ないという習慣を取り入れてみましょう。
② SNSの使用時間を制限する
スマートフォンにはアプリの使用時間を制限する機能が備わっています。1日30分〜1時間以内を目安に設定し、無意識な“ながら見”を防ぐといった工夫をしてみましょう。
③ 通知をオフにする
あなたのスマホに来るすべての通知が必要なわけではありません。必要最低限のアプリ以外の通知をオフにすることで、集中力が途切れる、スマホを触ろうとする回数を減らすことができます。
④ 対面でのつながりを大切にする
SNSの“つながり”だけでなく、リアルな会話や対面の交流を意識的に取り戻すことが、孤独感や不安感を軽減させます。週に一度でもいいので、友人や家族とじっくり話す時間を設けましょう。
⑤ 就寝1時間前はスマホを見ない
眠る前の1時間は、読書やストレッチ、日記などのアナログな時間に切り替えることで、睡眠の質が改善されます。ブルーライトを避け、心と体、脳をリラックスさせましょう。
おわりに
スマホは現代における必需品であり、完全に手放すことは容易いことではありません、それこそ便利な面も多くあります。しかし、『スマホ脳』が伝えているのは、「便利さの裏にあるリスクを知り、自分でコントロールする意識を持とう」ということです。
私たちの脳は原始時代大して変わっておらず、まだスマートフォンの刺激に適応しきれていません。だからこそ、使い方を意識し、心と脳の健康を守る選択がとても重要です。
今この瞬間から、スマホとの付き合い方を少しずつ見直してみましょう。それが、より豊かで充実した日々への第一歩となるはずです。
余談:筆者の体験談
私自身、スマホ依存症だった自覚があります。スクリーンタイムの1週間の平均が9時間だったなんてこともよくありました。そこからスマホ脳を読んだのですが、読んだからと言っていきなりスマホは1日1時間なんてできるわけもなく、スマホをやめてもパソコンでYouTubeやAmazonプライムを見たりしていました。
ですがデジタルデトックスをやってみて、失敗して、また初めて、失敗して、、、を繰り返し、少しずつスマホの画面と向き合う時間は減ってきました。昔より孤独感、虚無感は無くなったと思います。私自身まだまだ奮闘中ですが、ぜひ皆さんも少しずつスマホから人生を取り戻していきませんか?
それではまた!!
※このブログはアンデシュ・ハンセンによる著書『スマホ脳』を参考に執筆しています。
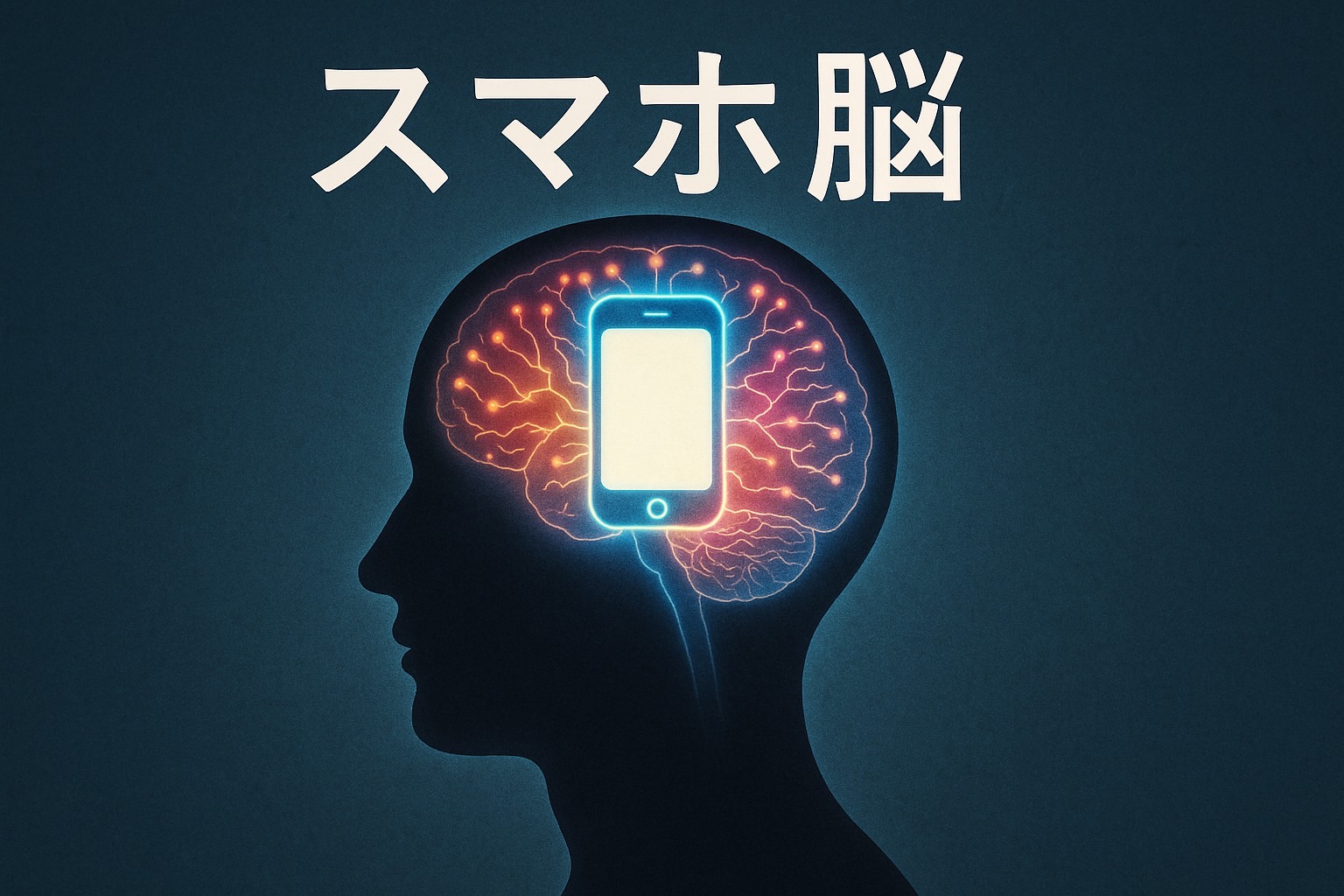

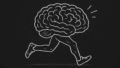
コメント